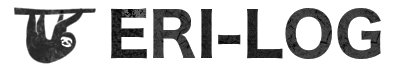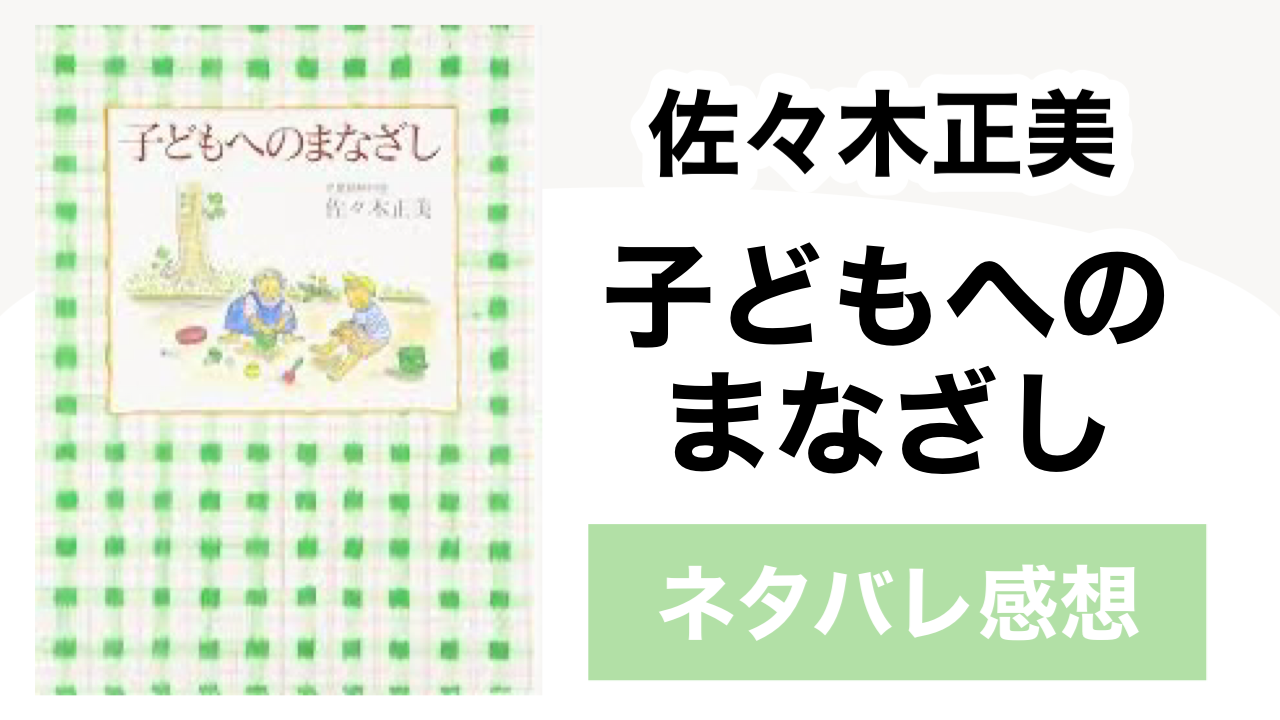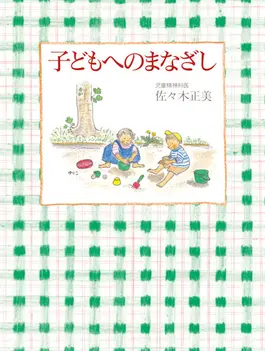佐々木正美「子どもへのまなざし」を読みました!
あらすじ、どんな人にオススメなのかなど、ネタバレ感想とともにがっつりご紹介します。
登場人物とあらすじ
<あらすじ>
子どもにとっての乳幼児期は、人間の基礎をつくるもっとも重要な時期です。
人を信じる力や感情の豊かさや貧しさは、十人十色です。
そして、人を信頼できるということが、豊かな人間関係をつくるための基本であり、それがいちばん育つのが乳幼児期だと、児童精神科医の著者は伝えます。
こんな人におすすめ
- 30〜40年前の育児本を読んでみたい
- 親族ぐるみ・地域ぐるみで子育てをしたい
- 子どもはとことん甘やかして育てたい
ネタバレ感想
乳幼児期の子どもをどう育てるか?そもそも育児はどうあるべきか?について書かれた本です。
まだ育児すべき子どもがおらず、子どもの気持ちも親の気持ちも持っている自分が読んでみて、大事だと思ったこと・感じたことを以下まとめます。
まず、子どもの育て方に関する ①子どもは子どもの社会で自己決定することを学んで成長していくので、親が過保護に心配しすぎない ②子どもは依存と反抗を繰り返して成長する ③子どもは親の言うとおりにはやらずに親のやるとおりにやる(親の行動を真似する) ④親自身が幸せでないと共感力は育たない という4点については、とても納得できました。
私はどちらかというと親が過保護かつ、両親があまり社交的なタイプではなかったために幼い頃からあまり同年代とのコミュニケーションを積極的にとらずに大人になりました。それで感じるのは、自分が30歳を超えた今でもコミュニケーションをとても下手だと自覚しているし、コミュニケーション自体をとても苦痛に感じているということです。
ただ、コミュニケーションを取ることで得られる楽しさや高揚感も理解しているので、もっとコミュニケーションの練習を幼い頃にできていればよかったなと思ってはいました。
なので、「子どもは子どもの社会で成長する」というのは理解できるし、自分の子どもにはそういった機会を与えたいなとは感じました。
親の言うようにではなく、親のやることを真似するというのも過去の自分に当てはまるし、子どもの前にまず親自身が幸せでなければ子どもを幸せにできないという言葉にも励まされました(子どもが生まれたら、身を粉にして子どものために尽くさなければいけないのかと思い込んでいたので)。
ここからは著者への疑問(?)、反論(?)となるのですが…
例えば、子どもが子どもの社会の中で理不尽な扱いを受けていた時、大人は黙って見ていていいのか?と思いました。声や力の大きい子がいつもわがままを言ったり、暴力を振るったりして、他の子どもが我慢していたり、嫌な思いをしていたら?その時は、大人が「我慢しなくていいんだよ」とその輪の中から外して、自分ひとりでも楽しい世界があるんだと教えてやるべきではないのか?声や力の大きいわがままな子を教育すべきではないか?
自分がもし幼稚園だとかでジャイアン的な同級生にいつも手下役やパシリ役をやらされていたら、親に助けてほしいと思うだろうなと思ったんです。なので、「子どもの社会のことは子どもに任せておけばいい。それで子どもは成長するから」というのは、それは本当に成長なのか?ただ我慢させているだけで、子どもの健やかな成長はむしろ阻害されるのでは?と思ってしまいました。
また、「まず親自身が幸せでなければ」と書いてある割に、夫婦仲は良くないといけない、妊娠中は穏やかでないといけない、出産直後から子どもの期待になるべくすべて応えないといけないと、「こうすべき」ことが山盛り書いてあるので、「結局どっちを重視したらいいの?」と困惑してしまいました。
しかも、どの「こうすべき」ということも「母親がやるべき」ことばかりで、筆者は男性にも関わらず、なぜ父親のやるべきことは全然書かれていないのかと思ってしまいました。
子どもは母親だけのものではないですよね。父親だって当然育児に参加すべきなのに、母親にばかり負担を押し付けるのでは、夫婦仲も悪化するし、妊娠中だって不安になるし、出産直後のボロボロの体にムチ打って子ども最優先にしていればうつ病一直線です。筆者は、あまりにも母親にプレッシャーをかけすぎているのでは…と感じました。
そして、読んでいて一番つらかったのが、「コミュニケーション下手な親の子どもは、良い子どもに育たない」という内容です。
筆者が言うには、親子関係もコミュニケーションの一種なのだから、他人とのコミュニケーションが苦手(例えば、頼ったり頼られたりする関係など)な親が、子育てをうまくできるはずがないとのこと。では、コミュニケーションが苦手だと自覚している人は、子どもを生んではいけないのでしょうか?コミュニケーションが苦手な親の子どもは、全員が不幸なのでしょうか?絶対に「良い人間」に育たないのでしょうか?
この、内向的、非社交的な親を追い詰めるような内容には、全く賛同できませんでした。どんな人間だって子どもを持ちたいという願いがあるなら子どもを持つ自由があるし、それを誰かに咎められたり、「その子は良い人間には育たないよ」なんて言われる筋合いはないと思います。
最後に、筆者は、豊かな社会になったことで親同士が泥臭いコミュニケーションが下手になり、それゆえに子どもとのコミュニケーションも取れなくなり、結果的に育児が下手な親ばかりになったと言っています(逆に言えば、戦前戦後の日本では、地域全体で子育てする環境が普通であり、親が泥臭いコミュニケーションに慣れていたため、子どもとのコミュニケーションも上手であり、子育ても上手だったと言うのです)が、本当にそうでしょうか?
戦前・戦後の育児が至高で、他の世代の育児はすべて「下手」だと断じてしまうことはあまりにも危ういと感じます。
それに、戦前・戦後にだって、そういった「地域ぐるみの育児」が嫌だと感じていた内向的な親たちもいたはずです。なのに、そういった人たちをまるでいないもののように扱っていることにも違和感を感じます。彼らにとって、当時の育児は本当に「最高」だったのでしょうか?もし本当に当時の育児が「最高」ならば、もっと日本から偉人が輩出されているのではないでしょうか?そうはなっていないところからして、当時の育児が現代と比べて「最高」ではないことは明らかなのではないでしょうか?
さらに言えば、現代、特に都会で生きる親たちは「地域ぐるみの子育て」をすることは絶対に叶わないのですから、当時は最高だった、今はだめだ、と言われたところで、「じゃあどうしたらいいの?」と途方に暮れてしまいます。
育児書というのは、今、育児をする時に何を気をつけたらいいのかを論ずるべきであり、「過去の方が良かった」と懐古主義に浸られても困ってしまうな…と感じました。
まとめ
Amazonの育児書ランキングで上位表示されていたので、購入した本でした。
「初めての育児を前に、何を気をつけるべきかを知っておきたいな」という前向きな気持ちで読み始めたのですが、うつ病持ちで内向的な性格の自分には非常につらい内容でした。
まるで自分をピンポイントに責め立てるような内容(「コミュニケーションの下手な親は子育てをうまくできない」だとか、「現代の親はコミュニケーションが下手だから育児も下手だ」など)に感じられて、途中で読むのを諦めそうになったほどです。
自分はやはり子どもを持ってはいけなかったのだろうかとひどく落ち込みました。
ただ、筆者は1935年生まれということで、30〜40年前の育児書としては良かったのかもしれません。母親が子どものわがままに何でも応えて甘やかすべき(父親の存在は基本無視)という論は、当時は主流だったのかなと感じました。
自分の祖父母世代の育児書を読んでみたい方にはおすすめかもしれません。しかし、シングルマザーやシングルファーザー、精神疾患のある方などにはあまりおすすめできない一冊でした。